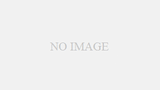・バスケットボールは昔50人対50人でやっていた。
(1892年コーネル大学では50人対50人で試合が行われたが、この試合について担任のE・ヒッチコックは「体育館が破壊されかねない」などと述べるなど逸話となっている。 プレーヤー人数については、その後次第に制限され、1894年にプレーヤー人数についてはフロア面積に合わせて5人、7人、9人とされることになった。というか人数が同じなら何人でもいいというルールだったのでそれ以上もあったかも知れない。バスケットボールが生まれたのが1891年だったので、人数制限なしの時代は短かった。)
・貼り絵で有名な山下清は、旅先ではなく家に帰ってから絵を描いていた。
(山下清は、1922年、東京府東京市浅草区田中町(現・東京都台東区日堤)に生まれた。翌年、東京大震災によって家が焼失してしまい、両親の故郷である新潟県に移住する。3歳のころに風邪が悪化して重症化、生死の境を彷徨う。一命はとりとめたが、命の危険にさらされ、この病で軽い言語障害と知的障害の後遺症が残ってしまう。父の死、母の再婚など紆余曲折があったが、1934年に千葉県の知的障害児施設・八幡学園に預けられ入園し、「ちぎり紙細工」に出会う。「ちぎり絵細工」に没頭した清は、1936年から学園の顧問医を務めていたであった式場隆三郎の目に留まり、式場の指導を受ける。、式場の指導を受けた清はさらにその才能を開花させていった。1938年には銀座で初の個展が、翌1939年には大阪で展覧会が開催され、清の作品は多くの称賛を浴びた。第二次世界大戦中の1940年、18歳のときに清は突如学園を脱走。それから1955年まで、約15年間絵を描きながら放浪の旅を繰り返したという。これが「放浪の画家」と呼ばれるようになったゆえんである。山下清は、放浪の旅の途中で見つけたきれいなものや珍しいものを作品に残している。このときの放浪の旅がテレビドラマ化され、大人気になった。ドラマでは風景などを見ながらその場で描いているような描写があったが、実際は家に帰ってから制作していたようである。清がこのような驚異的な記憶力を持っていたのは、知的障害のある人にまれに起こるという「サヴァン症候群」(サヴァン症候群とは、知的障害(知的発達症)(※1)や発達障害のある人が、特定の分野において突出した才能を持っている状態や、その人を意味する言葉である。 サヴァン症候群の人の中には、芸術や数学、記憶力などの分野で素晴らしい才能を発揮しながら働いている人もいる。)だったからではないかといわれている。花火がとりわけ好きだった清は、長岡や諏訪など全国の花火大会に足を運び、そのときの情景や感動をそのまま作品に残した。ミリ単位でちぎられた色紙を点描絵画のように貼り合わせ、複雑な色合いを表現している。実際に目にすると、その細やかさや迫力に驚く人も多いであろう。山下清作品は、その人気の高さや所属した画壇がなかったため、その作品の鑑定できる者がないこと、各地でお礼の為に作品を残したと言う影響から、贋作偽物を真作と偽ったの展覧会などが開かれることが多く問題になっているが、実際には貼り絵作品はほとんどが自宅家や八幡学園で制作されており、遺族が保管している。)
・ロダンの「考える人」は、考えているのではなく地獄で苦しむ人をただ見ているだけ。
(「考える人」という彫刻が、フランスの彫刻家ロダンによって作られたことは広く知られている。おそらく、美術に詳しくない人でも、作品名を聞いた時に思い浮かべることの出来る有名な作品であろう。 しかし、「考える人」と呼ばれる作品を想像出来ても「彼が一体何を考えているのか?」について知っている人はほとんどいないのが現状ではないだろうか。とても深刻そうな顔をして一点を見つめているが、彼は一体何を考え込んでいるのであろうか?
【実は考えているのではなく、見つめているだけ?】
実は作品名は「考える人」となっているが、彼は何かを考えているというより「見つめているだけ」なのである。もともと「考える人」という作品は、ロダンの「地獄の門」と呼ばれる巨大な彫刻作品の一部なのである。そして、「地獄の門」という作品の中で「地獄に落ちていく罪人を上から見つめている人」を切り取ったのが「考える人」である。そのため、何かを考え込んであのポーズを取っているというよりは、上から地獄へ落ちていく罪人を見つめるポーズといった方が正しいのかもしれないのだ。ちなみに「地獄の門」は高さが6メートル、幅が3メートルほどある巨大な作品で、罪人たちが地獄へ落ちていく地獄絵図が描写された作品である。この作品の上の方を観察してみると、しっかりと「考える人」が存在していることが確認できる。
【「考える人」のモチーフ】
元となった作品である「地獄の門」は、ボードレールの「悪の華」という詩集やダンテの「神曲」といった文学作品を参考にして作られた。一説によると、「神曲」の「地獄変」で、地獄を見て悩むダンテの姿がモチーフになったと考えられている。
また、「地獄の門」を制作している時にロダンが思い悩んでいたことから、ロダン自身がモチーフになったという説もある。この頃のロダンは、既に妻がいるのにも関わらず、教え子であるカミーユ・クローデルと恋に落ちていた。そのため、妻とカミーユの板挟みとなって、悩みこんでいる自分自身を作品にしたとも考えられているそうである。
【「考える人」は誰が名づけたの?】
実は「考える人」というタイトルを付けた人物は、ロダン本人ではない。「考える人」というタイトルは、ロダンの没後にリュディエという人物によって名付けられたものである。リュディエは、考える人という彫刻作品を「鋳造(熱してドロドロになった金属を型に流し込んで冷やし固める技術)」した人物として知られている。「考える人」は、元々は地獄の門という大きな作品の一部だったものが、別のタイトルが他者によって付けられたことで、別の解釈が加わった作品といえる。)